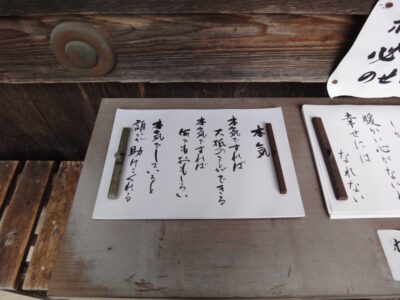-
令和3年1月 朝坐禅会「指月の会」案内
2021年1月24日諸行無常今年も宜しくお願いします。栃木県も年始から緊急事態宣言が出され、様々自粛や制限の中で日々を過ごしています。このコロナ禍を思うとき、時折学生時代に読んだ小説を思い出します。村上龍の書いた『ヒュウガウィルス』という本です。この作品の舞台は、第二次世界大戦で日本が降伏せず本土決戦を行い、数十年経ってもトンネルにこもってゲリラ戦が続く世界です。九州のヒュウガ村からエボラウィルスをさらに凶悪化したような病気が都市部に蔓延し、その対応のために軍の部隊が派遣され対処に当たるストーリーです。現地に到着しウィルスの猛威を目の当たりにし、うちひしがれて人間の弱さを嘆く兵士に科学者が言った言葉が強く記憶に残っています。「われわれの体を構成する分子は脆くて壊れやすいつながり方でつながっている。だから化学反応が可能で、全体として信じられないような生体のシステムが生まれた。強い結合で結ばれれば鉱物になってしまう。鉱物は何億年経ってもほとんど変化がない。人間は柔らかい生きものだ。その柔らかさ、脆さ、危うさが人間を人間たらしめている」私の中で「無常」の理解の土台ともなっている一節です。人は脆い、変化しやすいからこそ人たり得るのだ。それを嫌ってもそうでないならそれは人間ではない。変化するからこそ何かが起こる、何かが出来る。喜ばしいことも悲しいことも変わるからこそ変われるからこそ、無常だからこそなんだ。ならばそれは良い悪いで見るものではなく、世の道理、真理として受け入れていくものなのだろう。私たちは変わるからこそ、今のような人なのだろうから。このコロナ禍で激変してしまった時代、それでも私たちは生きています。環境変化の規模は大きくても生きることは変化し続けることです。この変化の中で、それでも僧侶としての本分を見失わず、為し得ることを探して行っていく。変化を受け入れ、そして本分を忘れないことが、今私ができる最善のことなのだと信じています。祥雲寺副住職 安藤淳之明日の朝坐禅会は略した形で6時半より行います。 -
令和2年12月 朝坐禅会「指月の会」案内
2020年12月27日正精進『八正道』先日NHKでやっている番組「ちこちゃんにしかられる」で、法事で読まれるお経って何のための物?という出題がありました。ちこちゃんの回答は「お経は生きている人へのお釈迦様からのアドバイス」というもので、これはとても今様な、いい纏め方をしているなぁ、と思いながら聞いていました。元来仏教は、この移ろう世の中(諸行無常)で、どうしたら心を穏やかにすることが出来るのかを突き詰めた宗教です。その為のお釈迦様や歴代の祖師方が説かれたアドバイスがお経です。様々種類はありますが、基本的には私たち生きている人間に生き方を説いた物が中心なのです。ご法事は、亡くなった人へのお祈りの為の機会です。故人に喜んでもらえるようにお供え物を用意して、在りし日を想い冥福を祈る時間です。この法事の時にお経を読むのは、伝統的には読経の功徳を故人の冥福への祈りに巡らし向けるという言い方になるでしょう。生きている縁者が、身心を正しその功徳をお供えして向こうで見守ってくれている故人に喜んでもらおう、という物です。何が一番喜んでもらえるかと想うならば、それは生きている縁者がしっかり立派に生きている姿を見せてあげる以上のことは、おそらく無いのでしょうから。 -
令和2年11月 朝坐禅会「指月の会」案内
2020年11月22日直指人心 見性成仏お寺の社会における役割を、私は二つのことに分類しています。一つには布教、修行道場としてのお寺。お釈迦様に始まり歴代の祖師方によって伝えられた仏法を、受け継ぎ育んでまた伝えていくこと。自身と信仰する人によって実践される場で有ること。即ち布教と実践道場としてお寺が有ることです。二つには慰霊供養の場としてのお寺。家族友人近隣の人、亡くなられた近しい人を送り弔い祀るのに相応しい、葬式法要を行う場としてお寺が有ることです。この二つをキチンと行う事が、社会で果たすべき役割で有ると思っています。ある時県内の老師のお話を聞いていて「亡くなった人を仏さまとして導き、残された遺族が仏さまとしていただくことが出来るようにするのが葬式だ」という言葉が耳に残りました。その時は良く理解できませんでしたが、後日になってこれなのかと思える出来事がありました。2年ほど前の冬、私に大変良くしてくれていた近所のおじさんと親戚のおじさんが立て続けに亡くなられました。一月ほど何をするにも手につかず、鬱々とした日々を送っていました。ある日の行事を行っている中、ふいに「亡くしてしまった人を思い続けてもどうにもならない。それよりも今あるご縁を大切にしなくては」と思いを転換することが出来ました。でもご縁を大切にといってもどうしたらいいのか?それこそ私を大切にしてくれたお二人にしてもらったことを、そのまま人にしてあげたらいいではないか。そう思い、諸事心がけて臨んでいると、人に親切にしてあげようとする行為の中に故人との思い出が蘇り、寂しさが少しやわらいで、故人のことを身近に感じることが出来るように思えました。故人を仏としていただくというのはこういうことなのではないか、今はそのように思います。まだ上手く整理して話せていませんが、もっと上手に伝えられるよう精進したいです。それが私がお寺を守り伝える人として、求められはたすべき役割なのだと思っています。祥雲寺副住職 安藤淳之当分の間6時半からの一座のみとなります。 -
令和2年10月 朝坐禅会「指月の会」案内
2020年10月25日正定『八正道』先日テレビをつけましたらNHKBS放送で『海のシルクロード、ブッダと宝石』という番組が放送されていました。1980年代に撮影されたものの復刻放送のようです。もう40年近く前のスリランカが撮影されていて、海上交易で栄えた遺跡や宝石の採掘、食文化民族問題などが取り上げられていました。昔のフィルムですので今よりだいぶ画質は荒いのですが、今よりもなお魅力的に映っている様に感じ、昔の日本からの海外の見え方はだいぶ違ったのだろうと思えました。スリランカは仏教国ですからもちろん仏教寺院や仏教文化遺跡も大きく取り上げられていました。とある厳しい寺院に許可を得て撮影班が入れたとのことで、荒野の真っただ中に十数人の僧侶が起居する様子が撮られていました。昔からのあり方を厳格に守るその僧院では、入門を許された後は指導すらされることもなく、やるべき事は経典の暗記と托鉢、そして瞑想のみだそうです。近くの集落まで十数キロ歩き、功徳を積みたい信徒から供養を受けてお経を読み上げ、戻って経典を読みそして瞑想を行う、これが修行の全てです。お釈迦様の教えに八正道があります。苦しみから離れようとするならば、8つの行いを正しく心がけなさい。それが苦しみを滅する道である、と説かれました。この八正道の一つが正定、正しい集中の仕方、心の定め方。これこそが世界中の仏教徒が瞑想を行い、また私たちが坐禅を行う基であるのです。国は違えど文化は違えど、同じ仏教徒であり同じく仏道を歩んでいる。同じ釈子、お釈迦様の孫子たる遠い遠い親戚筋を見ているようで、私も励みとせねばなぁ、と励まされる心地で見ていました。祥雲寺副住職 安藤淳之 -
令和2年9月 朝坐禅会「指月の会」案内
2020年9月26日今年は彼岸花も咲くのが遅く、それでもお彼岸中日には花開いてくれました。
他は是吾にあらず 『典座教訓』我が宗祖道元禅師は数多くの言葉を残されており、その中でも世間に知られた言葉と思います。他の人にやってもらうのは自分がしたものではない。自らのことは自分で行う。ごく当たり前のことを言っていますが、その真意は仏道を歩む姿勢そのもののあらわれであると思います。禅師が中国に留学して学んでいた際、あるお寺であったエピソードです。暑い時文、真昼の太陽が照っている中、日差しを浴びながら庭で椎茸を干している老僧を見かけられ、「貴方のような年功を積み重ねた方がこのような雑事をしなくても若い者にでも任せればよいのでは」という趣旨の言葉をかけられて、それに対して老僧は「他人にやってもらったのでは自分でしたことにはならない(他は是吾にあらず)」と返されたそうです。自らが成すべき事を、行う。自らの本分を全うする。当たり前のことに聞こえますが、そこにやらない理由をつけてしまう事を、私たちは当たり前のように行っています。それは惑わしとなり、煩い悩ますものとなりうるものです。身分や長幼の序等に依らず、成すべき時に成すべき事を自らが成せるように行う。惑わされないことを身と心に習わせ慣らしていく、習慣づけていく。これこそが仏道の修行と呼ぶべきものです。心を耕すあり方そのものです。盲目的に義務を果たすロボットになれ、などと言っているのではありません。自らを惑わす怠け心に陥ってはいないか身心を常にチェックして、出来ることを出来るときにやらず何時行うのか、ハッパをかけるように自身を鼓舞し習慣づけていく。そうすることで自らを良く整えていく。自らのなすことのみが自らに帰結するのですから。祥雲寺副住職 安藤淳之28日の朝坐禅会も6時半からの一座のみとなります。
宇都宮市の祥雲寺は歴史のある曹洞宗のお寺です。
栃木県庁のすぐ北にあり、自然林の中には西国三十三番の観音像が祀られています。
また、樹齢350年を超える枝垂れ桜の老樹は県天然記念物として有名です。
たくさんの方々に仏教を親しんでいただくことを願いとし、様々な信仰行事を催しています。